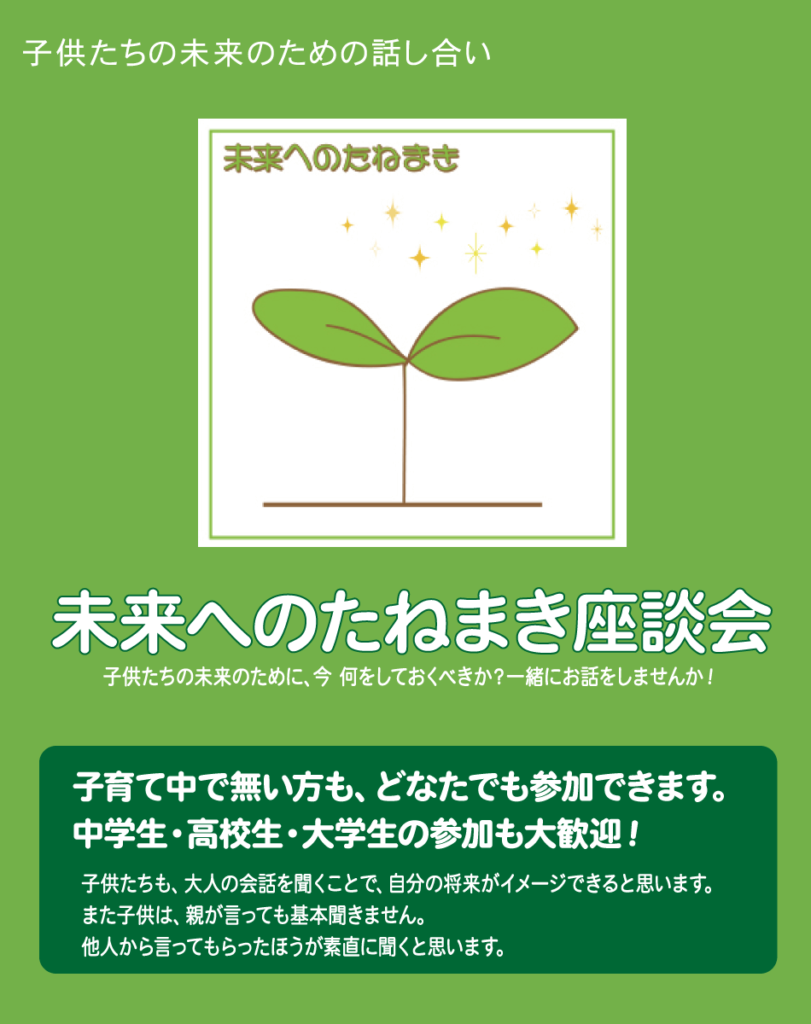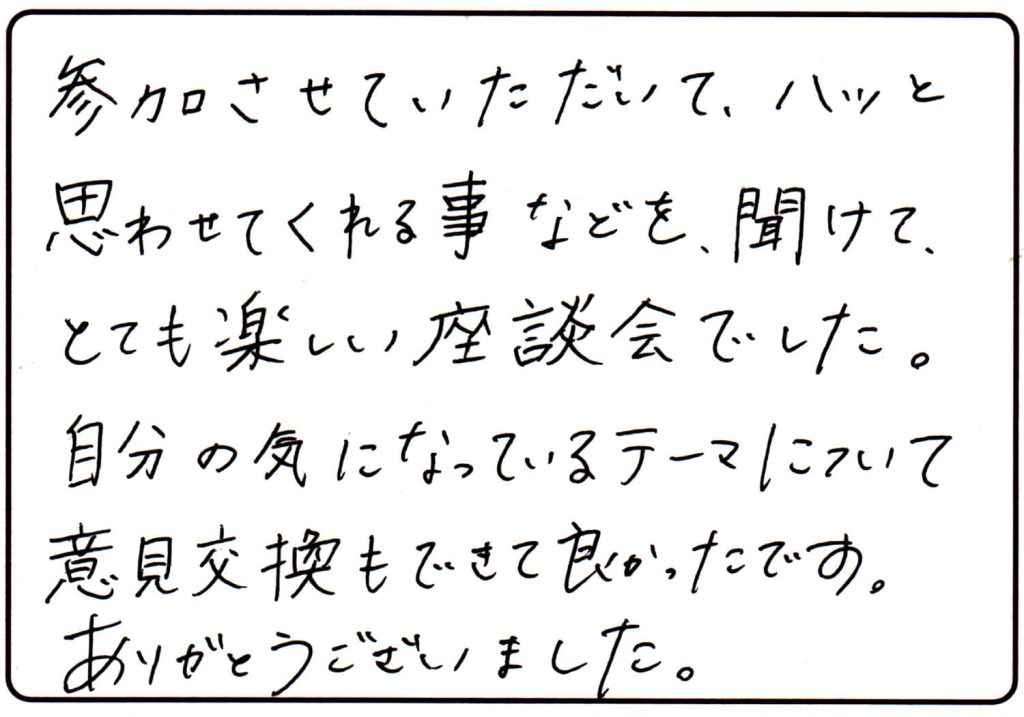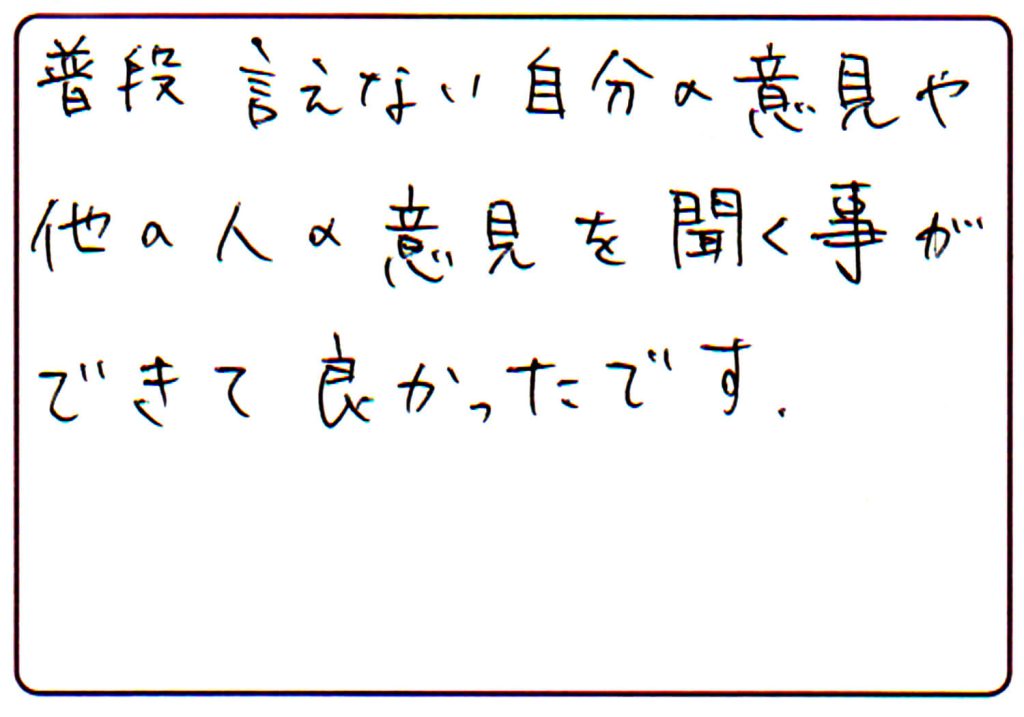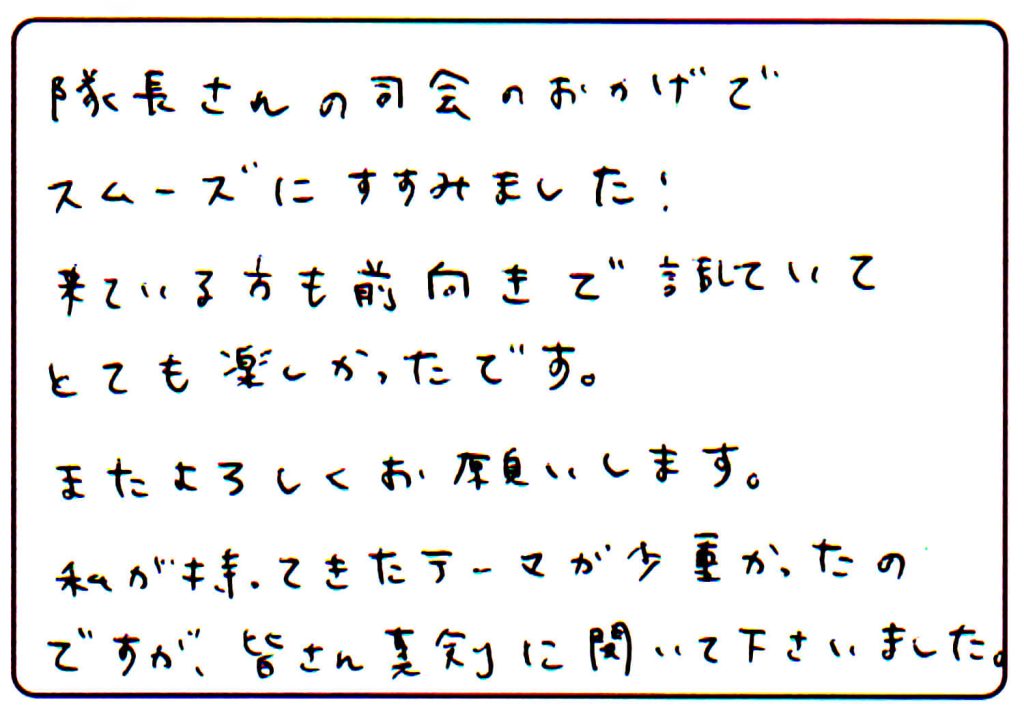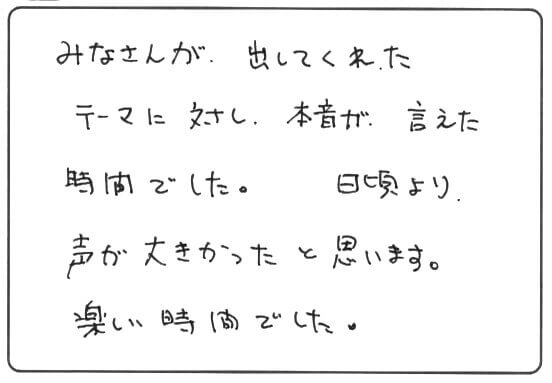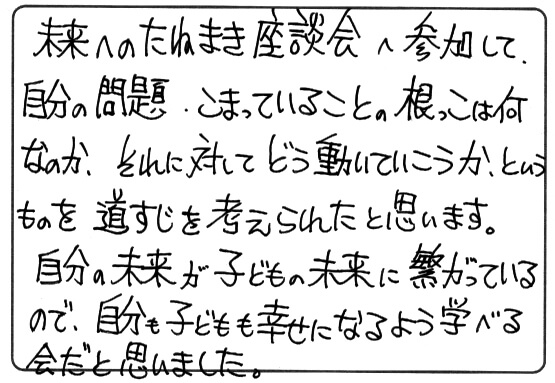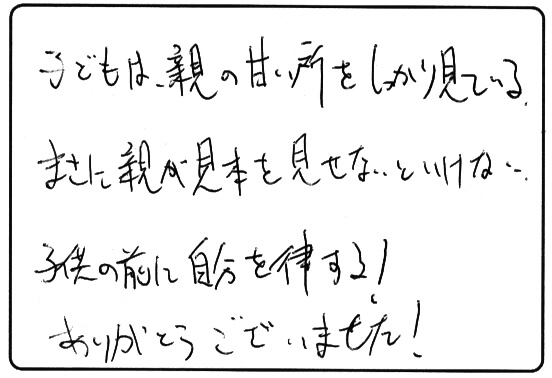もっと早く知っていれば・・・・
開催日時
開 催 日 (受付時間:17時50分・開催時間:18時~20時)
※たねまき座談会の開催日は、毎月第4土曜日になります。
①2022年10月15日(土)
②2022年11月26日(土)
③2022年12月17日(土)
④2023年1月28日(土)
⑤2023年2月25日(土)
※12月は第4土曜日がクリスマスのため、17日開催にしております。
※参加者によって座談会のテーマが変わりますがお好きな日程をお選び下さい。2回とも参加して頂くことも可能です。
参 加 費:500円(税込):(資料・飲み物・お菓子の費用)
参加人数:4名限定
開催場所:写真の松屋2Fスタジオ
持参するモノ:筆記用具
参加申し込みは、お電話で 0943-75-3577
お電話の際、スタッフに「座談会に参加したいです!」と言って下さい。
座談会のキッカケ
こんにちは!吉井町の「写真の松屋」店長の松尾勝彦です。
「未来へのたねまき座談会」を行っています。
キッカケは、僕は現在、6歳の男の子の子育てをしています。近い将来、確実にロボット、AIが生活の中に入って来ます。子供たちのために、「今」何を準備しておいた方が良いのか?あまり考える機会、話を聞く機会がないことに気付いたからです。そして心配になったことは、これだけテクノロジーが発達しているのにも関わらず、僕が子供の頃(40年前)に経験した教育と同じことを繰り返している気がしたことです。
そこで、子育てが終わった方や、子育て中の方、これから結婚をする方など、いろんな世代の方に集まってもらって、これからの子供たちの未来のために、今何をしておいた方が良いのか?を考える話し合いをしてみたいと考えました。お菓子を食べながら、リラックスした感じで行いたいと思っています。
参加して頂き、お子さんに対する、声掛けが変わる1歩になれば幸いです。
未来へのたねを、今から一緒に蒔きませんか!
中学生や、高校生、大学生にも、自分の将来を決めるための、とても良い大人の話が聞けると思います。
座談会のテーマは自由
座談会の大事にしたいことは、
①全員が話ができること
②相手の話を聴くこと
③相手の話を否定しないこと
このことを意識したいと考えています。
参加されるみなさん、多分 お話したいことや、知りたいことのテーマはバラバラだろうと思います。そこで、参加者お1人に対して、1つのテーマをご準備頂きたいと思っています。
もしテーマが無くても、こちらでご用意いたします。
例えば
- 子供たちの習いごと
- 賃貸派or新築派?
- おこづかいの渡し方
- 子供へのゲームの渡し方
- 子供の不登校について
- 良い習慣作りと悪い習慣作り
- NISAなどの投資の話
- 褒め方と叱り方
- 子供たちの進路(高校・大学・留学)
などについて、他にも聞きたいテーマがあれば教えて下さい。
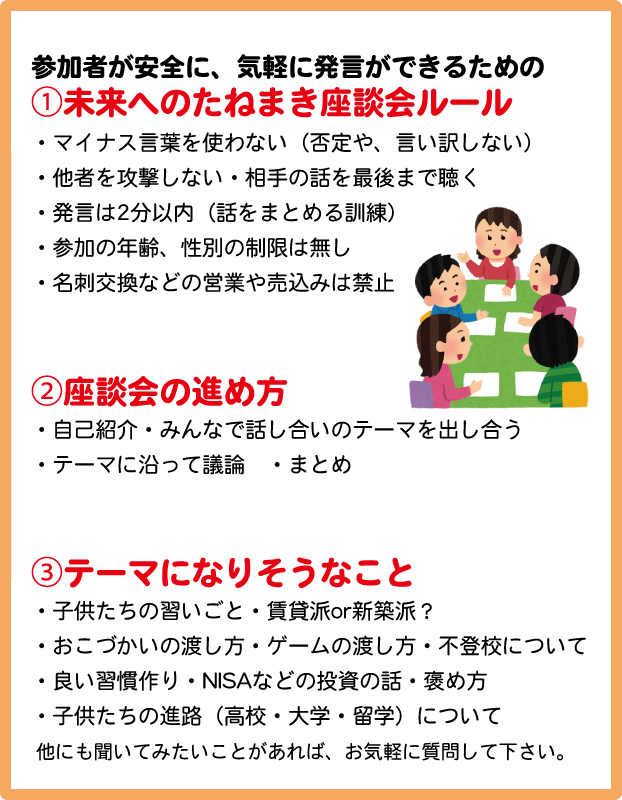
お子さん連れの参加もOK!
パパとママでお子さんを見て頂ければ、お子さん連れも可能です。またご夫婦も大歓迎!ぜひお友達も誘ってみて下さい。
座談会の進め方
タイムスケジュール
18:00 受付開始
18:10 座談会開始(アンケートに記入)
18:20 参加者の自己紹介
18:30 趣旨説明
18:40 座談会開始(6名×10分)
19:40 まとめ
19:55 アンケート記入
20:00 終了
参加者は最高6名です。
1つのテーマを、約10分間議論したいと思います。
1テーマ×6名=60分。
1つのテーマに対して、お1人2分以内で話をして行くことになります。たった10分なので結論を出すことは難しいかもしれません。ただいろんな意見の中から、自分に合った考え方を見つけて頂ければと思っています。
もし同じようなテーマを2名が出された場合は、時間を倍にして議論をしたいと思います。
最後に、15分ほどまとめの時間を設けています。
そのまとめの時間を使って、出して頂いたテーマで、もうちょっと深堀したいテーマに対して、多数決を取って議論をしたいと思います。
もしみなさんからのテーマがなければ、僕の方でテーマを準備しておきたいと思っています。
座談会に参加して頂いた方の感想
隊長さんの司会のおかげでスムーズにすすみました!
来ている方も前向きで話していてとても楽しかったです。
またよろしくお願いします。
私が持ってきたテーマが少重かったのですが、皆さん真剣に聞いて下さいました。
未来へのたねまき座談会へ参加して
自分の問題、こまっていることの根っこは何なのか、
それに対してどう動いていこうかという
ものを道すじを考えられたと思います。
自分の未来が、子どもの未来に繋がっている
ので、自分も子どもも幸せになるよう学べる会だと思いました。
座談会のテーマ
座談会のテーマをリストアップにしています。どんなテーマに興味を持ってもらいましたか?どうしても気になるテーマが、直近のことになるかもしれませんが、できれば自分の年令の10年後、20年後のテーマのお話をすることで、事前にイメージを作ることができますので、その年令になって問題が生じた際に対応できると思います。こちらにあげたテーマ以外の話題も大歓迎です。いろんなテーマがあると、座談会も盛り上がると思います。
0~5歳のテーマ
- 保育園や、幼稚園の選び方
- パートなどの仕事の探し方
- 習い事について
- 褒め方と、叱り方
- 優しさと、強さ
- 武道の大事さ
- 三つ子の魂
- 5歳からの教育
- 子供の自己肯定感を育てる
- 子育てが楽になる考え方
- くもんで学ぶ大切さ
- 読み聞かせ
- 時間の概念
- 片付けの教え方
- 男の子の育て方
- 抱き癖
- 他の子と比べない
- 夫の家事への参加
6~10歳のテーマ
- 学校の勉強について
- いじめ
- 不登校
- 自立をさせる子育て
- 友達の作り方
- 音読の大切さ
- 読書をする時間を作る
- お小遣い帳の付け方
- 子供のやる気の出し方
- 覚える力と、考える力の違い
- 勉強が好きになるために
- お家で勉強する習慣を身につける
- ゲームの渡し方
- 学校や、塾の先生の見分け方
- 片付けの習慣作り
- コーチングと、ティーチングの違い
- 友達の選び方と、作り方
- 家庭と、学校以外に第3の居場所を作る
- 自分のことを好きになること
- 未来から逆算する力を身につける(計画性)
- 金のタマゴを産むガチョウを大事に育てる
10代前半のテーマ
- 貯金の習慣作り(誰でもお金持ちになれること)
- 誰にでも成功者になれる
- 世界は広い(英語や、留学の経験をさせる)
- 若い時に挫折や失敗することが、大事なこと
- 欲求のコントロールの仕方
- 他人と比較しない
- 友人の受賞や成果を、妬むのではなく一緒に喜べる人になること
- 何になりたいか?と職業を選ぶのではなく、どんな人になりたいのか?を大事にする
- 社会に出ると、他人と違う方が評価されること
- 何かに挑戦すれば、必ずリスクが有ること
- パソコンのスキル(ワード・エクセル・Photoshop・Illustrator・WordPressなど)
- 目的が見つかると、勉強は楽しいこと
- 映画や、読書を通じて、自分の世界と広げること
- 一人旅の体験
- 「緊急でない、重要なこと(第2領域)」を優先すること
- 夢の叶え方
- 仕事の選び方(いろんな仕事があることを知る)
- リスクを取る勇気の持ち方
- 逆算して考える力を付ける(大人になると、勉強がしたくなるわけは?)
- 人生のメンター(師匠)を見つける
- 会社四季報の読み方(株式投資)
- 留学について
- 高校の選び方について
- 好きなことを仕事にするために必要なこと
- AIや、ロボットが普及する中での働き方(仕事の見つけ方)
- 言われたことしかできない人と、期待以上の事ができる人に違い
- 自分で考えて行動できる人になるためには?
- 少子高齢化になるということは?
- ローンを組ませないために必要なこと?
- 勉強ができなくても、得意を知り、伸ばす
- 気が利く人になるためには?
- 正しい会議の仕方を知っておくこと
- 安定より、変化に対応できる人になる
- スマホの渡し方
- 高校を卒業したら進学、または就職?
10代前半のテーマ
- マネーリテラシー(特に借金と、複利)
- お酒や、パチンコ、タバコなどの悪習慣の話
- 自立と依存の関係
- 高校生になったら「7つの習慣」を教えること
- 一人旅の体験
- 異性との付き合い方
- 依存しない人生を歩くために必要なこと
- 大学の選び方について
- アルバイトをする前に知ってほしいこと
- ひとり暮らしをする前に知ってほしいこと
- 性教育について
- 10代で子供を産むということは?
- 結婚について
20代のテーマ
- 結婚相手の選び方
- 家の買い方
- NISAなどの積立投資
- 離婚のリスク
- 複利の知識
- 家事の分担
- お酒との付き合い方
- 家族と仕事の優先の決め方
- 失敗の仕方と大切さ
- 傾聴する力を身につける
- 自分のミッションを見つける
- 何も考えていなければ自分で少子高齢化を招いている
- 不妊治療
30代のテーマ
- 子育て
- 子供の習い事について
- 夫婦でのお金の管理
- 株式投資
- 夫婦円満の秘訣
- 家族団らん
- リストラに合った際
40代のテーマ
- 会社をやめた時のこと
- 副業のこと
- 運動不足を解消
- メタボの解消
- 健康診断
- 遺産相続
- 親の介護
- 親との残りの時間の過ごし方
50代のテーマ
- 定年後の過ごし方
- 定年後の仕事の見つけ方
- 趣味の見つけ方
- 熟年離婚
- 配偶者との死別
- 自分の病気との向き合い方